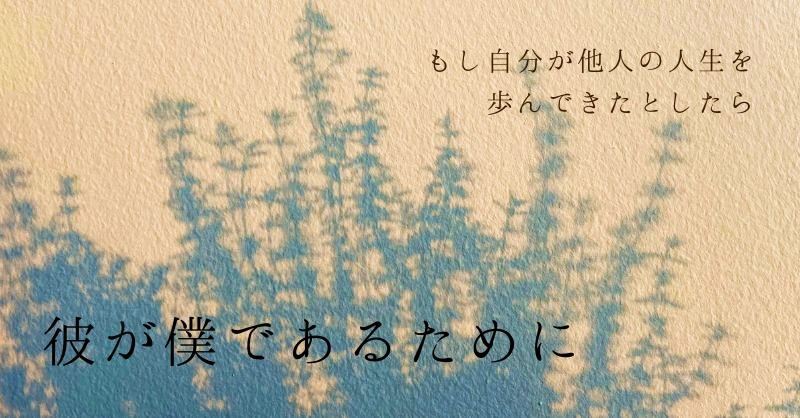「もし自分が他人の人生を歩んできたとしたら、それは不幸なことだろうか?」
川島光明氏の小説デビュー作『彼が僕であるために』は、読者にこの問いを投げかける。
これまで自分のものであると信じていた家や家族、そして名前まで。それらが本当は、他の誰かが受け取るはずのものだったとしたら?
赤子の「取り違え」という運命のいたずらによって、全く異なる人生を歩むことになった二人——茂利と弘幸。彼らは70年の歳月を経て再び巡り合う。
決して偶然ではなく、出会うべくして出会った二人が導き出した人生の答えとは何か。
『彼が僕であるために』の情報
- 著者:川島光明
- 出版社:文芸社
- 発刊日:2025/08/15
- 文庫判:144ページ
Source:文芸社
70歳からの”青春”
「青春」と言われて思い浮べること。
学園生活、制服、夏、部活、恋愛、文化祭……etc.
どんな場面を切り取っても、思い浮かぶのは高校生くらいの若者たち。失礼ながら、70歳という年齢は「青春」という言葉に似つかわしくないと感じてしまう。
しかし、本書に登場する茂利と弘幸が過ごした時間は、紛れもなく”青春”だった。
二人の物語は、公園で孫を遊ばせていた茂利が、同年代の弘幸と出会うところから始まる。初対面にも関わらず、馴れ馴れしく距離を詰めてくる弘幸に、茂利は戸惑いつつも、二人はすぐに意気投合する。
それから、弘幸が掲げた「自分の孫を持つ」という目標を達成すべく、茂利は弘幸の婚活に付き合うことになる。高齢になってからの新たな挑戦に戸惑いながらも、二人の間には強い友情が芽生えていく。
「まずこれから結婚をして、子どもを作るんだ。その子どもに早く結婚してもらって。できれば18歳くらいまでには。それで子どもを産んでもらうことで、孫を作るんだ」
川島光明『彼が僕であるために』P.20
「孫が欲しい」と言いながらも、結婚すらしていない弘幸。しかも、「20代の結婚相手」を希望している。念のために言っておくが、弘幸は茂利と同じ70歳である。
茂利は呆気にとられながらも、弘幸の協力をすることになる。
しかし、そこからの二人の行動は早かった。
出会いバーで若い女性に声をかけ、若い男女が集まるテニスサークルに飛び込み、マッチングアプリに登録して数人の女性と会うまでに進展した。
その行動力とスピード感は、まさに”青春”そのものであると私には感じられた。
なぜ弘幸は結婚相手に「20代の女性」などという、無謀すぎる目標を立てたのか?
思うに、目標は何でもよかったのではないだろうか。本書を読むと、弘幸の「孫が欲しい」という純粋な思いはひしひしと伝わってくる。
しかし、結婚相手や自分の子供のことをないがしろにするかのような弘幸の将来設計は、どこか常軌を逸しているように感じる。
これは、心の底では弘幸も、その目標が実現すると考えていなかったからではないか。それよりも、運命のいたずらで結ばれた老人二人で「青春」を謳歌することが、彼にとって重要だったのではないだろうか。
弘幸にとっての「婚活プロジェクト」は、茂利との「青春大作戦」の一部だったのではないかと、私は思う。
人は二度生まれる
茂利と弘幸の”青春”には意味がある。
そもそも「青春」とは何か。 辞書を引くと、次のように記されている。
せいしゅん【青春】
Oxford Languages
若い時代。人生の春にたとえられる時期。希望をもち、理想にあこがれ、異性を求めはじめる時期。
フランスの哲学者・ルソーは著書『エミール』に、次のような言葉を残している。
われわれは、いわば二度この世に生まれる。一度目は存在するために、二度目は生きるために。
ルソーが言う「第一の誕生」とは、生物としてこの世に生を受けること。そして「第二の誕生」とは、一人の人間として自我に目覚め、真に自分らしく生きようとすることを意味する。
彼らが、この世に生れ落ちてから70年の月日が経つ。しかし、茂利と弘幸が出会ったのも、「自分たちは何者か」を知ったのも、つい最近のことである。
「取り違え」についての事実を共有した二人が、とある事情で遠出した際に、弘幸は次のように述べている。
「ほら。僕たちだってもうこんな歳だけど、未だに生きる道に迷っているからね。このお墓参りだってそう。70歳にして、自分探しの旅をしているみたいなものなんだ」
川島光明『彼が僕であるために』P.114
これこそまさに「第二の誕生」。青年期の若者たちと同じように、彼らもまた、本当の自分を探し続けている。
彼らの”青春”は、まだ始まったばかりなのだ。
二人の出した答え
「もし自分が他人の人生を歩んできたとしたら、それは不幸なことだろうか?」
本書のテーマであるこの問いかけに、茂利と弘幸はどんな答えを出したのか。
「茂ちゃんは、取り違えられたことはどう思ってる? 不幸だと思う?」という弘幸の問いかけに、茂利は「何とも言えないなぁ」と煮え切らない返答をする(P.99)。
「取り違えられたって聞くと、大抵の人は『災難に遭った』って感想を持つと思う。でも、僕は違う。思いたくもない。だって、取り違いを受けたから、重い病気の治療を受けることができたし、整った環境で勉強もできた。茂ちゃんだって、多江さんと結婚できたし、陽輝くんていう可愛い孫も持てたんだ。幸せじゃない?」
川島光明『彼が僕であるために』P.100
そう、彼らは幸せだったのだ。紆余曲折はあれど、それらを乗り越えて、今この瞬間がある。
彼らは、それぞれが歩んできた人生を自分自身のものとして受け入れている。たとえそれが、本来であれば「入れ替わっていたはずの人生」だったとしても。
弘幸の計算によると、彼らの年代で赤子が取り違えられる確率は、わずか「0.0002パーセント」だそうだ。
「僕たちは、0.0002パーセントの確率で当たりを引いたんだよ」
川島光明『彼が僕であるために』P.100
「災難」であるはずの取り違えを、彼らは「当たり」と呼ぶ。これこそが、弘幸と茂利のたどり着いた答えだった。
まとめ:もしかしてだけど

本書の終盤で、伊藤光太郎という大学生の青年が登場する。
彼は自転車で日本一周の旅をしている途中、茂利と弘幸に出会う。
そこから、ちょっとした事実が明らかになり、それを受けて彼は日本一周を中断して東京に帰ることにした。
しかし、それはネガティブな理由からではなく、新しい目標が見つかったからだった。
『東京に戻ったら、お笑い芸人の養成所に通うことに決めました』
『もし芸人として売れたら、お2人のことを話してもいいですか?』
ここで、私はあることに気づく。光太郎、東京、芸人、もしかして……。
著者の川島氏は、実際に二人のような人たちに出会ったことがあるのかもしれない。
そして芸人として活躍した後に、約束通り、彼らの数奇な人生を小説として発表したのかもしれない。
もちろん、真相は不明である。これはあくまで一読者である私の勝手な妄想。
しかし、もし本当に、この0.0002パーセントの奇跡が地球のどこかで起こり、この物語が生まれたのだとしたら——なんて、思いを馳せてしまうのである。