一生懸命に努力して、何かを成し遂げる人はすごい。
しかし、努力をしたからといって、必ずしも何かを成し遂げられるとはかぎらない。
生きていると、そんなどうしようもないことが度々起こる。
そんなときに
「だったら、頑張っても意味ないじゃないか」
と諦めるのではなく、
「それなら、そこそこに楽しむ方法を考えてみよう」
というのが本書の目指すところである。
この本で伝えたいことはただ一つ。
pha『ゆるくても続く 知の整理術』P.3
“一生懸命、必死でがんばっているやつよりも、
なんとなく楽しみながらやっているやつのほうが強い”
ということだ。
京大卒・元「日本一のニート」の称号をもつphaさんの著書『ゆるくても続く 知の整理術』。
本書は、phaさんが普段から実践している「がんばらずに、なんとなくうまくいく勉強法」が書かれた、phaさん流の学習指南書である。
『ゆるくても続く 知の整理術』の情報
- 著者:pha
- 出版社:大和書房
- 出版日:2019/11/07
- 文庫:256ページ
Source:大和書房
この本の次に読んだphaさんの『しないことリスト』の感想はこちら。
「楽しいこと」だけ勉強する
「勉強」といえば「嫌なもの」というイメージをもっている人はきっと多いはず。
おそらく、ここでの「勉強」というのは「学校の勉強」を思い浮かべているのだと思う。
学校の勉強は面白くないけど、趣味のことを調べるのは楽しい。
つまり、自分の興味のあることを勉強するのは、本来楽しいことなのだ。
phaさんは「人間の体は、自分に必要なものはおいしく楽しく感じるようにできているのだ」と語っている。
知識についても同じで、そのときの自分に本当に必要な知識を得る作業は楽しい。もし勉強が楽しくないのだとしたら、その知識は自分には必要ないのかもしれない。
pha『ゆるくても続く 知の整理術』P.23
本当は必要ないのに、「人に言われたからやる」とか「みんながやっているからやる」という理由でやっているからじゃないだろうか。
そんな勉強は、やらなくていい。自分が本当に楽しいと思って、本当に知りたいと思うことだけ学ぶようにしよう。
たしかに、自分の好きなことだけ勉強できたらいいなと思う。
しかし、上の文章に続いて「……というのは一面の真理ではある。だけど、楽しいことだけやってうまくいったら誰も苦労はしない、というのも事実だ」とも、phaさんは言っている。
学校の勉強では、すぐには役に立たない知識を膨大に暗記して、テストで高得点を取るためにその知識を使いこなす必要がある。
それが自分の興味と一致していれば、学校の勉強も楽しく感じることができるけど、なかなか難しい。
だから、本書のような「なんとなく楽しみながら」続けられる勉強法が重要になる。
pha流「読書メモ」の取り方
本書の中で、個人的に一番参考になったのが、phaさんが実践している「読書メモ」の取り方である。
phaさんは、読んだ本の面白さや重要度によって、4つの段階に分けて記録をつけている。
- 重要度:ゼロ
そんなに面白くなかった
→感想は書かないが、読んだことを記録に残しておく - 重要度:低
何か所か面白い部分があった
→その部分だけ引用してメモする - 重要度:中
本全体が面白くて、何か所かメモするだけでは足りない
→本の面白さをまとめたメモを作り、読書ブログに投稿する - 重要度:高
「この本はすごい」「他の人にもこの本の良さを伝えたい」
→ブログやX(旧Twitter)に、本の良さを分かりやすく解説した文章を書く
私もこれまでにアナログ・デジタルを問わず、いろんな方法の「読書メモ」を試してきた。
しかし、読んだ本の内容をしっかりと記録しようとすると時間と労力がかかるし、逆に何も記録しないと本の内容をすっかり忘れてしまう。
その中で、phaさんの「本の重要度によって『読書メモ』の取り方を変える」というのは良いなと思った。
ちなみに、私の現在の「読書メモ」の取り方は、次の通り。
- 読みながら、面白いと思った部分に付箋を貼る
- 読み終えたら、読書メーターに登録して感想を書く
- 付箋を貼った部分の中で、覚えておきたい箇所を「読書ノート」に書き抜く
- 特に面白かった本は、「書評」と称した感想をブログに書く
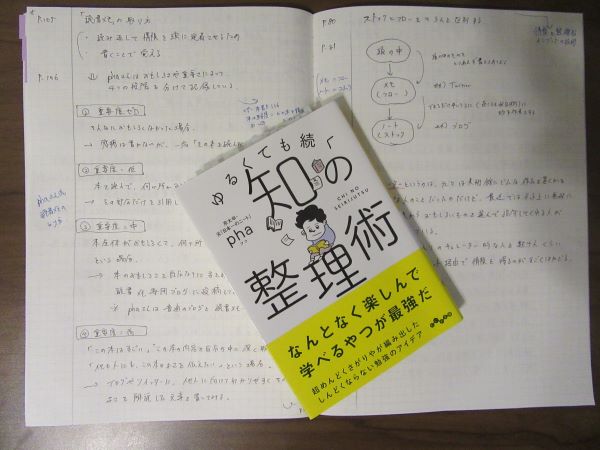
「読書メモ」の取り方は、必ずこうしなければいけないというものでもない。
いろいろ試しながら、自分に合った方法を見つけるのが一番良いと思う。
思考ツールとしてのブログ活用法
ブロガーとしても有名なphaさんは、ブログを書くメリットとして次の3つを挙げている。
- 脳内記憶装置の拡張
- 他人に教えると理解が深まる
- 他人からの反応で知識が広がる
それぞれの説明は省略するが、上の3つの共通しているのは「自分の知識を拡げて、理解を深める」という点である。
幸運なことに僕はブログの読者をたくさん得ることができて仕事にも繋がったけれど、もしそれほど読者がいなくて一銭にもならなかったとしても、ブログを書くことはやめていなかっただろうと思う。
pha『ゆるくても続く 知の整理術』P.141
なぜなら、僕がブログを書くのはあくまで自分のためだからだ。
(中略)
もちろんブログに書くときは人に読んでもらうことも意識するのだけど、それはあくまで二次的な目的にすぎない。自分の脳の拡張の思考ツールとして書くというほうが重要だ。
ブログを始める人の大半が、「収益化してお金を稼ぐこと」を目的としている。
このブログも収益化しているものの、私がブログを始めたきっかけの一つは、phaさんのブログの考え方を「いいなぁ」と思ったことだった。
自分が学んだことや考えたことを、好きなように置ける(書ける)場所をネット上に作りたい。それがブログを始めた最初の目的だった。
ブログをお金稼ぎの道具にするのもいいけれど、phaさんの言うように自分の思考を拡張するツールとして、もっと自由に、気楽に書いてもいいと私は思う。
まとめ
phaさんは、本書の「おわりに」で次のように語っている。
別に僕が偉いわけじゃない。こんなものはたまたまだ。
pha『ゆるくても続く 知の整理術』P.247
たまたまもらったものだからこそ、こんなものは一人で独占するものじゃないし、多くの人に共有されるといいなと思っている。
知識は人を自由にする。そして、知識は誰のものでもなく全人類に共有されるべきものなのだ。
何かを知らないことで困ることもある。
逆に、何かを知ってしまうことで苦しく感じることもある。
知識は人を自由にする。そして知識を得た後、それをどう使うかが重要である。
苦しい受験勉強とかはもうやりたくないけど、phaさん流の勉強法ならこれからも続けられそうだ。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
(ご質問・ご感想はこちらからどうぞ)



