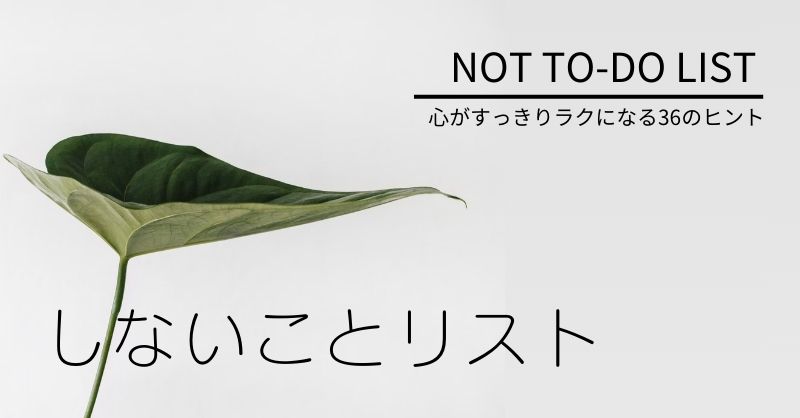元「日本一のニート」の称号を持つphaさんの著書『しないことリスト』を読んだ。
本書を読んで、私はあることをやめた。それは「Xの相互フォロー」である。
「相互フォロー」というのは、SNSでユーザー同士がお互いにフォローし合うことである。
これまではXのフォロワーを増やすために、自分から積極的に他者のアカウントをフォローしてきた。
そして、知らない人であっても、誰かにフォローされたらフォロバする(フォローし返す)ようにしていた。
しかし、本書を読んでそれが「自分にとっては不要なこと」であると気づいた。
この記事では、phaさんの著書『しないことリスト』を読んで、私が「Xの相互フォロー」をやめようと思った3つの理由をご紹介していく。
『しないことリスト』の情報
- 著者:pha
- 出版社:大和書房
- 出版日:2018/09/10
- 文庫:208ページ
Source:大和書房
過去に読んだphaさんの『ゆるくても続く 知の整理術』の感想はこちら。
あなたが本当に「しなきゃいけないこと」とは?
本書では「これは別にしなくてもいい」という36個の項目を、次の4つのカテゴリーに分類して紹介している。
- 所有しないリスト
例:余計な買い物をしない、自分だけで独占しない - 努力しないリスト
例:自分を大きく見せない、一人でやろうとしない - 自分のせいにしないリスト
例:二択で考えない、同じ土俵で戦わない - 期待しないリスト
例:仕事に身を捧げない、長生きしない
著者のphaさんは、本書を書いた目的を次のように語っている。
いわゆる「しなきゃいけないこと」の99%は「本当は別にしなくてもいいこと」だ。この本は、世間で「しなきゃいけない」とされていることを一つ一つ検討していって、「あれもこれも別にしなくてもいいんだ。人生ってもっと幅があるものなんだ」と、少し力を抜いてラクに生きていけるようにするために書いた。
pha『しないことリスト』P.7
上の引用の「99%」というのは、いわゆる”言葉のあや”だと思う。
とはいえ、「しなきゃいけない」の大半は「したら得するかもしれないけど、必須ではない」ことだと、個人的には思っている。
この「しなきゃいけないこと」の呪縛を解くためには、自分の頭で「何が大切なのか」を考える必要がある。
結局、自分の頭で「それは本当に自分に必要なのか」と一つ一つ考えていくしかない。評価基準を自分の外に置いている限り、他人に焦らされるのは避けられないからだ。
pha『しないことリスト』P.11
そのためには、次の2つのポイントを押さえることが重要だとphaさんは語る。
- 他人や世間の評価で行動を決めるのではなく、自分なりの価値観を持つこと
- 他人や世間のペースに無理してついていこうとせず、自分のペースを把握すること
この「自分なりの価値観を持つ」「自分のペースを把握する」というのは、他の何よりも優先して「しなきゃいけないこと」ではないかと思った。
「他の人がやっているから」「いま流行っているから」という理由ではなく、自分の頭で考えて「今の自分にはそれが必要だから」という自信を持って、判断できるようになりたい。
私が「Xの相互フォロー」をやめた3つの理由
冒頭で、本書を読んで「Xの相互フォローをやめた」と書いた。
といっても、『しないことリスト』に「SNSの相互フォローをやめる」ように書かれていたわけではない。
本書に書かれていた次の3つのことを知って、「Xの相互フォローは必要ないな」と私自身で判断した。
これらについて、1つずつご紹介していく。
人間の「注意資源」は有限
仕事や勉強を長時間していると、だんだん集中力が切れてやる気がなくなってくる。
その状況は、心理学用語を用いて「注意資源が枯渇したから」とも言える。
「注意資源」とは、人間が何かに注意を向けるときに使われるエネルギーのことである。
ここで重要なのは、「人間の注意資源(エネルギー)は有限」ということ。
つまり、人間が一日のうちに集中して取り組める作業量には限度がある。
そう考えると、なるべく自分の「やりたいこと」「やるべきこと」にエネルギーを割きたい。
しかし、人間は意外と無駄なことに多くのエネルギーを費やしている。そして、本人はそのことに気づいていない場合も多い。
「新しいものを手に入れるために、古いものをどんどん手放していこう」とphaさんが言うように、私も自分の「注意資源」の使い方を見直そうと思った。
人間が変わる3つの方法
本書では、経営コンサルタントの大前研一氏の言葉が、次のように引用されていた。
ある日ネットを見ていたら、経営コンサルタントの大前研一さんの次のような言葉を見つけて、「たしかにそうだな」と納得した。
“人間が変わる方法は3つしかない。
pha『しないことリスト』P.105
1番目は時間配分を変える。
2番目は住む場所を変える。
3番目はつきあう人を変える。
この3つの要素でしか人間は変らない。最も無意味なのは、「決意を新たにする」ことだ。”
調べてみると、こちらの言葉は大前研一氏の『時間とムダの科学』という本が出典らしい。
この言葉で重要なのは、「決意を新たにするだけでは意味がなく、環境を変えることでしか人間は変わらない」ということである。
先日、あるブロガーさんと交流する機会があった。
そして、その方が実践している取り組みや、これまでどのような経験をしてきたかなどの貴重なお話を伺うことができた。
ブロガーさんから良い刺激をもらい、ブログに向けるモチベーションが高まった。しかし、私の性格上、それが一時的なものであることが分かっていた。
モチベーションが下がるのを防ぐために、私はまず身近な環境から見直そうと思った。
そして、前述した相互フォローをやめてからは、Xから入ってくるブログの情報の質は以前よりも良くなったと感じる。
人間の「決意」は時間と状況によって変化しやすいけど、一度構築された「環境」は容易には変化しない。
本気で自分を変えたければ、一度環境を見直すのが手っ取り早い方法なのかもしれない。
ダンバー数(Dunbar’s number)
諸説はあれど、人間が安定した社会関係を維持できるのは平均「150人」ほどらしい。
この「150人」という数字は、「ダンバー数」と呼ばれている。
「ダンバー数」は、イギリスの人類学者・進化論学者であるロビン・ダンバー教授によって提案された。
彼は、霊長類の「大脳新皮質の厚さ」と動物の「平均的な群れの大きさ」に相関があることを見出し、そこから人間が安定して関係を維持できるのは「150人程度」であると推定されたらしい。
「ダンバー数」については、私は本書を読んで初めて知った。
ただ、これまでは何となく「友達100人できるかな」に影響されて、仲良くできる人数はそのくらいなのかなという気はしていた。
そして今回、Xの相互フォローをやめてフォロー整理を行っていたところ、偶然にもフォロー数が「ダンバー数」である150人に落ち着いた。
「ダンバー数」という概念を知ったことが、Xの相互フォローをやめた直接的な理由というわけではない。
でも、よく知らない人たちの情報に振り回されるよりも、(SNS上であっても)親しく交流してくれる人たちを大切にしたいと思い、過度なフォローは控えることにした。
まとめ:自分だけの「したいことリスト」を作っていこう
今回は、phaさん著『しないことリスト』を読んで、私がXの相互フォローをやめるきっかけとなった以下の3つの内容をご紹介した。
- 人間の「注意資源」は有限である
- 自分を変えるには、まず環境を変えるべき
- 人間が安定した関係を維持できるのは150人程度(ダンバー数)
前述したとおり、『しないことリスト』に「SNSの相互フォローをやめる」ことが書かれているわけではない。
情報であふれる現代において「こういう考え方もあるよ」と、凝り固まった考え方をほぐしてくれるのが本書である。
その本書のおかげで、私は「しないこと」を一つ達成することができた。
「しないこと」を自分で見つけることができれば、おのずと自分の「するべきこと」「したいこと」も見えてくるはず。
たぶん、「何がしたいか」「何をするべきか」を探していくのが、生きるということだ。
pha『しないことリスト』P.198-199
人生の「したいことリスト」は自分で作っていこう。
これからの人生で「しないこと」も「したいこと」も、自分の頭で考えて見つけていこう。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
(ご質問・ご感想はこちらからどうぞ)